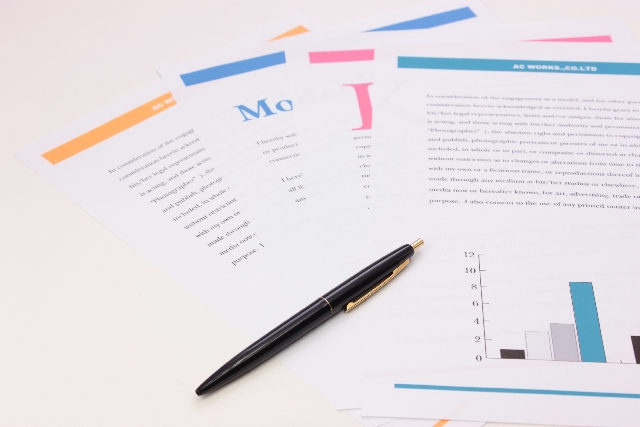


退職届けの受理についての質問です。
先日(6月15日)に直属の上司に辞意表明し、(6月末退職と記載の)退職届提出した所「自分では受理できないので更に上の上司に報告する」と言われて3日、直属の上司及び更に上の上司何も動きがありません。社内規定では14日前までに退職届け提出と記載ありますが、この場合自身で製作した届けの退職記載日(6月末)以降出社拒否は可能でしょうか?又、未受理を理由に拒否された場合の良い反論はありますでしょうか?できれば会社に反論できる様法律関係の説明も交えて教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
先日(6月15日)に直属の上司に辞意表明し、(6月末退職と記載の)退職届提出した所「自分では受理できないので更に上の上司に報告する」と言われて3日、直属の上司及び更に上の上司何も動きがありません。社内規定では14日前までに退職届け提出と記載ありますが、この場合自身で製作した届けの退職記載日(6月末)以降出社拒否は可能でしょうか?又、未受理を理由に拒否された場合の良い反論はありますでしょうか?できれば会社に反論できる様法律関係の説明も交えて教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
期間を定めない雇用契約なら、日給月給なら民法627条1項、完全月給制なら同2項が適用されます。日給月給なら、人事権を持つ者に意思が到達してから2週間後に任意退職となります(提出した日からの2週間ではありません)。
民法の規定は強行規定であるという地裁判例はあります。任意規定という考え方もありますが、就業規則が14日前までに提出となっているので、直属の上司に提出してから14日後に退職ということになります。
退職願ではなく、退職届となっているので、労働契約の合意解約の申し込みではなく、辞職意思の通知ということになりますから、承諾(受理)の余地はなく、通知した時点で有効であると主張することは可能ではないかと思います。
法的には、任意退職は人事権を持つ者に通知した日は数えずに2週間後が任意退職ですので、直属の上司がその日のうちに人事権を持つ者(経営者か人事部)に退職届をまわしていないのであれば、任意退職の効力の生じる日は提出日からの2週間後よりあとの日になるということにはなりますが、就業規則が14日前までに提出となっていますので、退職届に記載した退職日(6月30日)の次の日(7月1日)から出社しなくてもさしつかえないということになろうかと思います。
会社が退職処理を拒むということはあるかもしれませんが、その場合は、雇用保険手続きはハローワークから、社会保険は年金事務所から、源泉徴収票は税務署から催促してもらうしかないと思います。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
民法の規定は強行規定であるという地裁判例はあります。任意規定という考え方もありますが、就業規則が14日前までに提出となっているので、直属の上司に提出してから14日後に退職ということになります。
退職願ではなく、退職届となっているので、労働契約の合意解約の申し込みではなく、辞職意思の通知ということになりますから、承諾(受理)の余地はなく、通知した時点で有効であると主張することは可能ではないかと思います。
法的には、任意退職は人事権を持つ者に通知した日は数えずに2週間後が任意退職ですので、直属の上司がその日のうちに人事権を持つ者(経営者か人事部)に退職届をまわしていないのであれば、任意退職の効力の生じる日は提出日からの2週間後よりあとの日になるということにはなりますが、就業規則が14日前までに提出となっていますので、退職届に記載した退職日(6月30日)の次の日(7月1日)から出社しなくてもさしつかえないということになろうかと思います。
会社が退職処理を拒むということはあるかもしれませんが、その場合は、雇用保険手続きはハローワークから、社会保険は年金事務所から、源泉徴収票は税務署から催促してもらうしかないと思います。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
ハローワークに行きだして、半年経ちまして、焦ってる今日この頃です。なかなか書類選考の会社に面接まで、いかずに落とされるのですが、書類選考で、通るこつか何か有りますか?
ハロワに重点をおいて就活されてるようですが、競争率が半端ないです
書類選考というより、求人票の掲載期間が長い為、特に中小企業はこれといった方が現れない限りなかなか採用しませんよ
・・・
このままですとズルズルと行ってしまいますから別の媒体もご活用されて気分を変えて下さい
私も苦戦しましたが、期間が長引けば長引く程、段々と身体が怠けて、きつくなります
インターネットでの応募も併せてなされているかと思いますが、私の感触ではこちらの方が可能性は高いと思いますし、又、身近なチラシの求人も捨てたものではありませんので、広い視野で活動なさって下さい
書類選考というより、求人票の掲載期間が長い為、特に中小企業はこれといった方が現れない限りなかなか採用しませんよ
・・・
このままですとズルズルと行ってしまいますから別の媒体もご活用されて気分を変えて下さい
私も苦戦しましたが、期間が長引けば長引く程、段々と身体が怠けて、きつくなります
インターネットでの応募も併せてなされているかと思いますが、私の感触ではこちらの方が可能性は高いと思いますし、又、身近なチラシの求人も捨てたものではありませんので、広い視野で活動なさって下さい
知り合いが、失業保険を受給しているにも関わらず、居酒屋でアルバイトをしています。
何度か忠告はしましたが、聞きません。
ハローワークは社会保険に加入していなければ発見は難しいと聞いたことがありますが、年末調整か何かの際に発見する方法はないのですか?
何度か忠告はしましたが、聞きません。
ハローワークは社会保険に加入していなければ発見は難しいと聞いたことがありますが、年末調整か何かの際に発見する方法はないのですか?
アルバイトしても見つかる可能性は低いです。
密告でバレル事が多いんです。
バイト先の人たちや、知人には絶対内緒にしないといけません。
密告でバレル事が多いんです。
バイト先の人たちや、知人には絶対内緒にしないといけません。
関連する情報