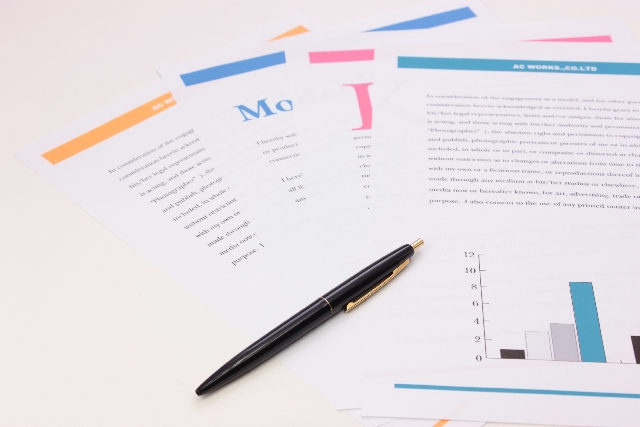


妊娠のためハローワークに受給期間の延長に行ったのですが、、、
妊娠のためハローワークに受給期間の延長に行ったのですが、振込口座等も聞かれず、仕事が出来るようになったらまた書類を持って来て下さい。と言われただけでした。受給期間の延長以外にしないといけない手続きがあるのでしょうか?
受給期間延長とは何ですか?
何も知らなくてごめんなさい。回答お願いします。
妊娠のためハローワークに受給期間の延長に行ったのですが、振込口座等も聞かれず、仕事が出来るようになったらまた書類を持って来て下さい。と言われただけでした。受給期間の延長以外にしないといけない手続きがあるのでしょうか?
受給期間延長とは何ですか?
何も知らなくてごめんなさい。回答お願いします。
早速ですが・・・・
失業保険(基本手当)とは
①働く意思があり、かつ働くことのできる状態にある
方が受給できる給付金です
②受給期間(手当を受け取ることができる期間)は離職日の翌日から1年
③給付日数は離職理由・加入期間・年齢等により90日~360日
④支給開始時期は待機期間7日経過後の8日目から。ただし、一般の離職者はさらに給付制限3カ月経過後。つまり、一般の離職者は7日+3か月経過後からの開始
これが基本となります。
★★★
さて、本題です。
上記が基本になりますが、当然例外もあります。
①についてですが、別の方の回答にもありましたが、怪我や病気、また主様のような妊産婦などは「働く意思」はありますが、「働くこと出来る」状態にはありません。
ですから、基本手当を受けることができません。
では怪我や病気が治ったり、出産しいざ働ける状態になった時点で、基本手当を受けようとしても
②の受給期間を過ぎてしまっている場合もあり得ます。
となると、そういった場合、基本手当を受ける資格を失効してしまいます。
そうならないための「受給延長手続き」です。
>受給期間の延長とは何を延長してるのでしょうか??
受給期間というのは離職してからカウントダウンが始まります。
上記でも少し触れましたが、この1年の間に手続きを開始し受給を終えなくてはなりません。
別の方が例を出されていましたが、離職の翌日に事故にあい7カ月の傷病となった場合、その間手続きはできませんよね。
ですが、刻々とカウントダウンはなされ、その方の受給できる期間は減っているわけです。
7ヶ月後にやっと手続きができたとします。
ですが、まず7日間の待機期間があります。そして、この方が一般の離職者であった場合、給付制限3か月がつきます。
なので実際に給付が開始となるのは離職から約10ヶ月後となります。
で、給付日数が90日だった場合、60日は離職から1年以内なので受給できますが、あとの30日は離職から1年を超えているので30日分は失効となります。
こうならないために「受給延長」をするわけです。
何を延長しているのかといえば、このカウントダウンをすることを延長しているのです。
要は、「受給延長手続き」はこのカウントダウンの時計を止める行為です。
ですが、この時計(延長期間)は最長でも3年です。
3年たてばまたカウントダウンが開始されます。
別の方が最長4年とされていますが、これは延長期間3年+受給期間1年=4年です。
ですから、3年7カ月に手続きしても上記の傷病の例に当てはめれば、30日は受給できないことになりますので、要注意です。
>手続きをした今日から3ヶ月は待機になるんですか、、、
離職者にはいくつか種類があります。
倒産やリストラなどの会社都合で離職された方=特定受給資格者
自己都合=一般の離職者
”正当な理由のある”自己都合=特定理由離職者
等々・・・。
このうち、特定受給資格者及び特定理由離職者は待機期間7日のみとなります。
一般の離職者は給付制限がつくので、7日間+3か月後に給付開始となります。
さて、主様の場合ですが・・・・。
延長手続きをされたわけですよね。
ということは、上記でも触れましたが、今は受給期間のカウントダウンをストップさせいる状態です。
ですから、受給開始はあくまでも主様が働ける状態となり「求職活動」に入ったときになります。
さらに、妊娠・出産の場合、離職しただけでは、一般の離職者扱いです。
ですが、この延長手続きをとることにより「正当な理由のある自己都合」として認められ『特定理由離職者』となり、いざ求職活動を始め受給手続きをとったなら、待機期間7日のみとなります。
失業保険(基本手当)とは
①働く意思があり、かつ働くことのできる状態にある
方が受給できる給付金です
②受給期間(手当を受け取ることができる期間)は離職日の翌日から1年
③給付日数は離職理由・加入期間・年齢等により90日~360日
④支給開始時期は待機期間7日経過後の8日目から。ただし、一般の離職者はさらに給付制限3カ月経過後。つまり、一般の離職者は7日+3か月経過後からの開始
これが基本となります。
★★★
さて、本題です。
上記が基本になりますが、当然例外もあります。
①についてですが、別の方の回答にもありましたが、怪我や病気、また主様のような妊産婦などは「働く意思」はありますが、「働くこと出来る」状態にはありません。
ですから、基本手当を受けることができません。
では怪我や病気が治ったり、出産しいざ働ける状態になった時点で、基本手当を受けようとしても
②の受給期間を過ぎてしまっている場合もあり得ます。
となると、そういった場合、基本手当を受ける資格を失効してしまいます。
そうならないための「受給延長手続き」です。
>受給期間の延長とは何を延長してるのでしょうか??
受給期間というのは離職してからカウントダウンが始まります。
上記でも少し触れましたが、この1年の間に手続きを開始し受給を終えなくてはなりません。
別の方が例を出されていましたが、離職の翌日に事故にあい7カ月の傷病となった場合、その間手続きはできませんよね。
ですが、刻々とカウントダウンはなされ、その方の受給できる期間は減っているわけです。
7ヶ月後にやっと手続きができたとします。
ですが、まず7日間の待機期間があります。そして、この方が一般の離職者であった場合、給付制限3か月がつきます。
なので実際に給付が開始となるのは離職から約10ヶ月後となります。
で、給付日数が90日だった場合、60日は離職から1年以内なので受給できますが、あとの30日は離職から1年を超えているので30日分は失効となります。
こうならないために「受給延長」をするわけです。
何を延長しているのかといえば、このカウントダウンをすることを延長しているのです。
要は、「受給延長手続き」はこのカウントダウンの時計を止める行為です。
ですが、この時計(延長期間)は最長でも3年です。
3年たてばまたカウントダウンが開始されます。
別の方が最長4年とされていますが、これは延長期間3年+受給期間1年=4年です。
ですから、3年7カ月に手続きしても上記の傷病の例に当てはめれば、30日は受給できないことになりますので、要注意です。
>手続きをした今日から3ヶ月は待機になるんですか、、、
離職者にはいくつか種類があります。
倒産やリストラなどの会社都合で離職された方=特定受給資格者
自己都合=一般の離職者
”正当な理由のある”自己都合=特定理由離職者
等々・・・。
このうち、特定受給資格者及び特定理由離職者は待機期間7日のみとなります。
一般の離職者は給付制限がつくので、7日間+3か月後に給付開始となります。
さて、主様の場合ですが・・・・。
延長手続きをされたわけですよね。
ということは、上記でも触れましたが、今は受給期間のカウントダウンをストップさせいる状態です。
ですから、受給開始はあくまでも主様が働ける状態となり「求職活動」に入ったときになります。
さらに、妊娠・出産の場合、離職しただけでは、一般の離職者扱いです。
ですが、この延長手続きをとることにより「正当な理由のある自己都合」として認められ『特定理由離職者』となり、いざ求職活動を始め受給手続きをとったなら、待機期間7日のみとなります。
有限会社 日本軽便急送という会社ご存知ですか。
熊本県菊池市泗水町に有限会社 日本軽便急送という会社があるのですが、ご存知ですか。
ハローワークに「ロードサービス隊員」で求人が出ているのですが、JAFのような仕事なのでしょうか。
必要な免許・資格には普通自動車免許のみで、整備士等は書いてありません。
もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
熊本県菊池市泗水町に有限会社 日本軽便急送という会社があるのですが、ご存知ですか。
ハローワークに「ロードサービス隊員」で求人が出ているのですが、JAFのような仕事なのでしょうか。
必要な免許・資格には普通自動車免許のみで、整備士等は書いてありません。
もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
当該会社は、初めて聞く社名ですが、おそらく、「赤帽」のように、軽自動車による配達業でしょう。
この業態に配送業は相当数ありますが、問題も抱えています。
まず、使用する軽自動車を購入させられる。車両代金は3~5年間の分割ですが、その他の実費、修理代、メンテナンス、燃料代、税金などは、加入者(運転手)の負担です。その他、荷物の送料(売り上げ)の中から、本部へロイヤリティーを払うシステムです。
この業態に配送業は相当数ありますが、問題も抱えています。
まず、使用する軽自動車を購入させられる。車両代金は3~5年間の分割ですが、その他の実費、修理代、メンテナンス、燃料代、税金などは、加入者(運転手)の負担です。その他、荷物の送料(売り上げ)の中から、本部へロイヤリティーを払うシステムです。
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。
※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。
※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。
本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。
よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。
よって、就業手当申請はしないこと。
②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。
受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。
よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。
よって、就業手当申請はしないこと。
②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。
受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
関連する情報